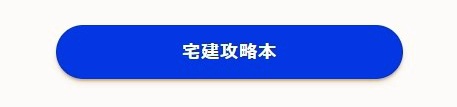効率が全然違う!宅建問題集の本当に正しい使い方を実演します!
【独学初心者の落とし穴】効率が全然違う!問題集の本当に正しい使い方を実演します!宅建、行政書士、賃貸不動産経営管理士、ファイナンシャルプランナーなどあらゆる資格に使える方法です。
宅建攻略は過去問中心の勉強
宅建の勉強をするにあたり、思っている以上に勉強時間は確保できないものです。「1日1時間の勉強をしよう」と決めつけてしまうと、なかなか継続できません。思わぬ障害にあたってしまいます。
例えば、あなたが会社に勤めている状況であれば、勉強時間に多くの時間を割くのは困難ですね。ただでさえ、仕事で疲れて帰ってきて、勉強しようと思ってもすぐに寝る時間が訪れてしまいます。
残業なんかがあり、同僚とつい一杯なんて日は、まったく勉強できない日もあるでしょう。
忙しい日々を過ごしていれば、思ったような勉強が進まないまま、あれよと、試験まであと3ヶ月しかない、1ヶ月しかないといった状況に追い込まれてしまいます。
試験が近づくにつれて、「難しくなる」といった情報が目に入ってきたら「あれも、これもも」と手を付けてしまい、「過去問題集だけでは合格できないのでは?」と不安になります。
あらゆる宅建の教材だけが増えていき、少しも手を付けられないまま本試験に挑み、「不合格」という結果になるケースが非常に多いです。
しかし、宅建の過去問題をベースに勉強を進めていれば、短い時間でもすべて勉強に当てられていれば合格できていたかもしれません。勉強の方法を間違えるな」ということです。
宅建試験勉強は勉強時間を確保することが大事といわれますが、それよりも、「短い時間をいかに効率的に使うことができるか」がより大事です。
やみくもに宅建勉強しても宅建試験には合格しません。結論としまして、宅建は過去問を中心に学習を進め、宅建の勉強方法を大きく間違えないことです。