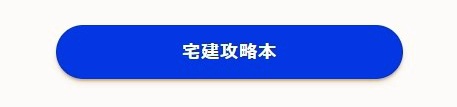宅建試験のはじまり
宅地建物取引士試験は昭和33年から始まりました。

宅建試験には長い道のりがありました。
昭和39年までは「宅地建物取引員」という名称で試験が始まりました。この年の受験者数は36000人で合格率93%と高い合格率でした。試験問題数はなんと30問で、権利の変動(9~12問)、法令制限(6~9問)、宅建業法(4~6問)、税法その他(5~8問)といったところです。この時代は、宅建業法の出題は比率的には高くなかったのが特徴です。当初は、法令集が持ち込んで試験を受けることができましたので今とは考えないくらいハードルが低かったようです。
「宅地建物取引主任者」となったのが昭和40年からです。
この時代には問題数が40問になりました。このころから受験者数は10万人をこえ合格率も30%を切りました。受験料は500円ですが当時としては決して安くはないのです。試験内容は、権利の変動(9~14問)、法令制限(9~11問)、宅建業法(8~13問)、税法その他(5~14問)といったところです。この時代の試験問題の大きな変化は、税法その他の比率が下がっていることです。昭和42年では14問ありましたが、昭和55年では6問になってしまいました。気になる合格基準は24点前後の水準で推移していました。
宅建問題が50問になったのは昭和56年からです。
この時期になりますと宅建合格率はついに20パーセントを切り合格率は16パーセント前後で推移していました。受講料は5000円と上昇してきました。宅建試験受験者数は10万人から後半は20万人に届くところに来ました。宅建試験構成は権利の変動(15問)、法令制限(10~13問)、宅建業法(15~17問)、税法その他(7~9問)となっています。
宅建試験合格発表は「不動産適正取引推進機構」のHPで、平成14年,15年で様変わりしました。合格発表は、各都道府県での掲示は3日間でしたが,平成14年から、宅建合格基準点・合格者の受験番号を、平成15年から、宅建問題の正解番号を公表するようになりました。
平成14年からは
情報公開の制度が変わり、宅建試験合格点が発表されるようになりました。これにより宅建試験合格ラインの推測があらゆるところでなされることになりました。
5問免除制度は平成9年から開始されました。平成9年度より、財団法人・不動産流通近代化センターの実施する「指定講習※」の修了者を対象に、5問免除される制度が始まりました。
平成27年4月1日より
「宅地建物取引士」に名称が変わりました。「宅地建物取引主任者」が国家資格の「士」の仲間入りとなり「宅地建物取引士」に名称が変わりた。今後試験の難関度に影響してきそうな予感がします。