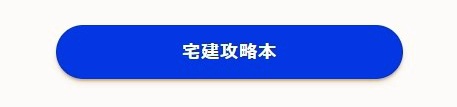宅建士の概要
【国家資格解説】宅地建物取引士(宅建は最強なんよ!)

この資格は不動産業にはなくてはならないものになっています。
「宅建」という言葉を聞いたがあるかもしれませんが、意外に知らない方もいます。
この宅建資格をとるには、実際に、1年に一度の国家試験を受けで合格しなければなりません。
宅建資格を知らなかったという方は、今から、どんな資格なのか説明させていただきます。宅建は、不動産業における専門家、エキスパートと称する国家資格です。不動産業で、5人に1人以上この宅建士という資格を持った人がいないと営業停止になってしまいます。
不動産業には非常に高価な財産であるのが現状です。法律では、この国家資格を持った宅建士という人がいないと営業できませんので、不動産業における専門家ということになります。
よって、不動産業に勤めている方は持っていて当たり前という資格になっています。
宅建資格のメリット
宅建資格は、実務生活に活かせる資格として国家資格の登竜門となっています。
特に不動産業で働いてない方でも、家やアパートを借りて住んでいる方などは、業者さんにだまされる恐れがあります。
宅建士の資格をとり宅建の知識を身につけることで、未然にトラブルを防ぐことができます。
たとえば、「格安物件だから」と、説明をしっかりと聞かずに契約すると、法律の規制があり、「思うように建物が建てられない」などというトラブルが予想されます。
自分の身を守るという意味でも、この宅建士の資格取得のメリットがあるということができます。