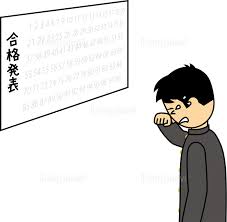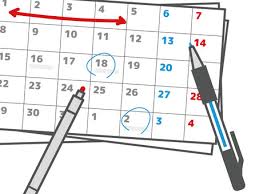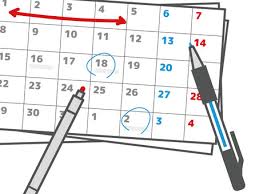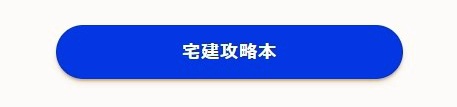宅建試験独学勉強法 5月までにやること
宅建試験独学で2回落ちて3回目で受かった!落ちたからこそわかるいい勉強法悪い勉強法
宅建試験落ちた方のための攻略法
5ヶ月くらいできっちりと抑えて行かなければならないこと。
実行項目
・実力をつけなければならない事項の強化
・試験の解き方と、試験時間内にきっちりと実力発揮できるようトレーニングする。
去年落ちた方であれば、なぜ落ちたか原因の追及をする
1.宅建に落ちたら何をすべきか検討する
宅建の勉強をある程度勉強された方。過去に宅建試験を受けている方は、権利関係、法令上の制限、宅建業法この辺りの全体像を理解されていると思います。そういった方は、5月から今何をすべきなのか。というのを説明させていただきたいと思います。
5月、6月に入ると思いますが、宅建の本試験は、10月の中旬くらいということになります。今の勉強方法を続けていくと行った中で、去年落ちた方であれば、なぜ落ちたかと言うことをもう一度考え直すこと。
また゛受けてはないけれども、今現状、ある程度もう権利関係、宅建業法、法令上の制限をやった方であれば、その方も、ちょっと考えてください。
2.宅建に落ちた原因は2つある。
実力をつけなければならないという事項と、試験の解き方、試験時間内にきっちりと実力を発揮という要素。この二つの要素は同じくらい重要です。
2つの要素を5ヶ月くらいできっちりと抑えて行かなければならない。というのが皆さんのやるべきことです。
以外に去年あたり受験された方ですと、33点ギリギリで落ちてしまったという方は、実際はそんなに実力がないにもかからず、「ある」と思っている方が多い。
十力がないにも関わらず、実力があると思っている方。
こういった方というのは、一番多くて、「ある」と思いながらずっと進んで行って、結局本試験で不合格になるケースです。原因も時間が足りないと思ってしまうわけです。
更にまた、受験して落ちてしまう方が多いんですね。「実力がある、ない」の根拠について皆さんに考えてもらいたいんです。ちょっとひねられた問題が出た場合、きっちり解けるかどうかの問題を。
皆さん勉強で、過去問題をやっていると思いますが、過去問以外の問題もやっていると思います。例えば、予想問題で、きっちり確認できているか分かると思います。
毎年、1.・2点差で落ちている方がいると思いますが、その方は「ある程度実力がある」と思っていた。しかし、実力テストをやってみると解けなくなってしまう。その方は、その時に気づくわけです。
実際、「自分は実力がない」ということを。
そこで、徹底的な復讐をやれば、ある程度実力はついていると思いますので合格できると思います。そういう方もいらっしゃるわけですね。
ですから、この二つは非常に重要です。
宅建試験合格のための対策
1.宅建問題を徹底的に理解する
皆様はある程度勉強されていますので、全体の理解はされていると思います。いわゆる権利関係、宅建業法、法令上の制限。去年受けられた形であればもうやってますね。後は、徹底的に理解することなんです。いわゆる、細かい部分をきっちり押えていく、物事の本質を理解する。
例えば、取得時効前の第三者と、取得時効後に現れた第三者では話が違いますね。遺産分割協議前と、遺産分割協議後の処理の仕方が違うわけですから。これをどのように違うのかとある程度理解しないと単に覚えているだけじやあないですか。
「こちらは二重譲渡の関係、こちらは違うよ」とか。そんな浅い理解ではなくて、ある程度深い理解まで持っていく。そうすると、若干ひねられても対応できるんです。さらに他の所でも適用できるようになってきますしと。そういったことを押さえていくということが重要になってくるんです。
その理解というのは、意外と予想模擬試験をやっても、過去問題をやったとしても、載ってないんですよ。テキストにも載ってないものが以外意外と多いんです。
ですから、過去問やったりテキストで見てみたりしても、なんかしっくりこないという問題ありませんか。権利関係に限らずです。例えば、土地区画整理法とか、都市計画事業法とかありますが、都市計画法も、条文はそのままだから、その答えというのは確かなんです。しかし、その中には深い内容が詰まっているわけです。大きな流れの中に、都市計画を決定する。決定してから次の段階またありますよね。
認可とか、あったりして、全然違ってくるわけなんですね。大きな流れが、それぞれの問題が都市計画事業のどこの問題なのか。どこに関して問われているものなのか。というものを理解していないと、実際の本試験では解けません。
土地計画法もそうです。土地区画整理法についても、施工者が違うわけですね。個人施行の場合もあれば、組合施行の場合、国とか地方公共団体とかといった公的施工の場合もあります。この3社違うわけですね。
その違いというものをきっちり覚えていく。そういったものを、分けて覚えていないと実際に試験に出た時に解けませんこれをきっちり比較対照しながら、解説している過去問題とか、予想問題とかを勉強していく。そういうことを、5月以降にやっていくことになります。
2.宅建模擬試験対策
模擬試験は大体7月~8月くらいにやる方が大半です。私からしてみると、7月とか8月の辺りでそうすると、もう遅いんですよね。実力がある程度ついていれば、これでいいんですけども、試験時間が足りというのは克服できません。
なぜかと申し上げますと、予想模試とかには試験の解き方が書いてないわけですから、やって時間が足りなかった。でも、対策の方法がわからない。だから違う模擬試験もやります。やっても、結局対策の仕方がわからないので、また同じことの繰り返しなんですよね。
それがズルズル続いて本試験。結局、試験時間が足らないで終わりです。それではもったいないですね。実力が到達しているのに「時間がたりない」というのは、もったいないんですね。制限時間ないで終わらせるためにはどうしたらいいのか。
「制限時間内で自分の実力発揮するための方法」ってどうやって行ったらいいのか。というものを説明してありますので、ぜひ読んでいただいて、早い段階でまず訓練するというのは、この二つをきっちり克服することができるんですね。
あわせて読みたい
宅建独学3月からのスケジュール編
【宅建試験勉強は3月からのスケジュールが大切です】 どうしても合格したい・・どうすれば・・ https://youtu.be/AscOWqaUoJA?si=d76gkE2zJBq6JCYb 宅建試験に間に合う3…
あわせて読みたい
宅建試験6か月前の宅建独学の勉強方法は?
【宅建試験までに6か月を切った時の勉強方法】 宅建試験まで6ヶ月、今何をすべきか?【宅建独学勉強法】 https://youtu.be/SWfT1oCuhPI?si=RB_ash9lUVKKoPvh 宅建過去…