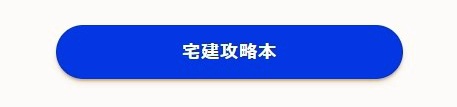宅建試験合格するために400時間も勉強する必要なし!
大切なことは、計画性を持ってとにかく続けること。資格9つ取った私の経験から合格するために必要な勉強時間を徹底解説。1年分の学習計画。【宅建一発合格】
【宅建一発合格】宅建試験合格するために400時間も勉強する必要なし!大切なことは、計画性を持ってとにかく続けること。資格9つ取った私の経験から合格するために必要な勉強時間を徹底解説。1年分の学習計画。
宅建試験100時間やれば合格するという間違った考え

100時間の根拠が全く分かりません!要注意です!!
宅建試験の独学勉強は100時間で合格すると聞きました。
どうやらある疑問が浮き彫りとなってきました。
100メートル競走では、あんたは50メートル先、私はスタートラインでよーいどん!!
学校で、法律の勉強は終わっている方と、これから法律を勉強する方では、勉強する時間はかなり差が出てきます。
ですから、法律の勉強がすでに終わっている方は、宅建一発合格も可能になります。
しかし、これから初めて法律を学ぼうとする方は、100時間ではかなり厳しくなってきます。
そもそも、100時間というのは、自分のレベルで発信しているものであって、平均的な勉強時間300時間よりもかなりかけ離れています。
このようなことから100時間で合格することはかなり厳しい設定と言えるでしょう。
宅建試験勉強はどれくらいの時間設定がいいのか?
まとめ
- 学習経験と背景: 不動産に関する経験や前提知識がある場合、試験の内容を理解しやすくなることがあります。初めて学ぶ場合よりも効率的に学習できるかもしれません。
- 学習方法: 学習方法によっても時間に差が出ます。効果的な学習計画を立て、適切な教材や講座を利用することが大切です。
- 学習時間: 100時間はかなりの学習時間ですが、試験の難易度や範囲によっては不十分な場合もあります。試験内容に合わせて学習時間を調整する必要があります。
- 個人の学習ペース: 人によって学習ペースは異なります。一部の人は短期間で多くの情報を吸収できますが、他の人は時間がかかる場合もあります。自身の学習ペースを把握し、それに合わせて計画をたてることが重要です。
- 模擬試験の結果: 合格に自信を持つ前に、模擬試験を受けて実際の試験に向けて準備を進めることをお勧めします。模擬試験の結果を基に、弱点を特定し、それに焦点を当てた学習を行うことが合格に繋がります。