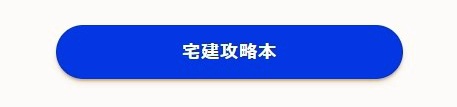民法を初めて学ぶ方のためにすべきこととは?
【宅建今が合否の分かれ道】権利関係、民法の壁にぶつかって心が折れそうになっている人に重要なアドバイス。急に難しくなって困っている初心者受験生に伝えたいこと。
- 法律用語に慣れる。
- 点と点が線でつながる
法律を人から教わったことがない方
宅建に合格するためには重要です。
民法がさっぱりわかりません。合格できるか自信がありません。
先にいます。大丈夫です、それが普通です。民法は宅建に限らず、マンション管理士、管理業務主任者試験にも、共通して出題される項目なので、避けて通れない道ですが、攻略が難しいのも事実です。民法の学習で挫折しかけている人向けに、どうやって学習をすればいいのかについて解説をしたいと思います。
例えば、こんな方いらっしゃいませんか。宅建業法と法令上の制限をクリアして、権利関係に突入したらあまりの難しさに全然進まない。「民放はこんな難しい。宅建試験ってこんなに難しかったの」そんな状況におちいっている方いますよね。
なぜかといいますと、私がそうだったからです。私、生まれてこの方法律というものを人から教わったことございません。民放どころか、宅建業法すら理解に時間がかかりました。そんな私が、市販の参考書だけで完全独学で合格ができたのは、勉強を苦手なりの学習のポイントを身につけたからなんです。
初心者の民法学習のポイント。それは、ズバリ一回で理解できると思わないことです。宅建に合格するためには、すごく重要なんです。宅建業法や法令上の制限というのは法律ですから、多少の難しさはあるものの、読めばわかるじゃないですか。おそらく。この二つの分野で意味が分からなくて、「なんじゃこりゃ」ってなってる方は非常に少ないと思います。
そういう部分は非常に限定的じゃないかなと思います。この二分野をクリアして、意気にのってる状態で権利関係の民法に突入すると、制限行為能力者だとか、連帯債務とか、契約不適合責任なんて言う難しい単語が立て続けに出てくるので、「何これ、宅建ってこんな難しいの、もうやってられない」「これは、ちょっと試験無謀だったかな」なんていう風に面くらっちゃうんです。
「やっぱり、俺には、宅建なんて無理だったのかなあ」なんて思ってらっしゃる方いらっしゃいませんか。まず先にいます。大丈夫ですこれが普通です。受験生時代の、私の心境そのままなんです。民放で、かなり跳ね飛ばされました。民法の学習で重要なことは、1回で理解できると思わないことです。難しいんです。
(令和01年問07)過去問題
Aを売主、Bを買主として甲建物の売買契約が締結された場合におけるBのAに対する代金債務(以下「本件代金債務」という。)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- Bが、本件代金債務につき受領権限のないCに対して弁済した場合、Cに受領権限がないことを知らないことにつきBに過失があれば、Cが受領した代金をAに引き渡したとしても、Bの弁済は有効にならない。
この問題、何わかりますでしょうか。いいですか、答えを聞いてるんじゃないんです。意味わかりますか。大丈夫ですか。わからないって言っている人いるんじゃないでしょうか。分からない方大丈夫です。最初はそんなもんなんです。
意味不明なんです。権利関係の問題というのは。受領権限って何? 弁済って何? 過失って何? いきなり勉強初めて、こんなに単語出てきたら「わけわからん」ってなりますよね。単語一つ一つが難しいんです。これが権利関係民法なんです。
民法という問題は、1回やってそれで理解ができると思わずに、いろんな問題を何度もやっていくってことが、とっても大切なんです。ポイントは、二つあります。これがすごく重要なんです。
1. 法律用語に慣れる。
民法には、このように難しい法律用語が共通語のようにバンバンでてきます。まず、これに慣れるということが大切なんです。なぜなら、本番では選択肢を選んで考えている時間はないんですよ。できるだけ一発で、何を言っているのか理解する必要があるんです。
なぜなら、試験では2時間しかないんです。2時間で50問解かなければいけないんです。これは、繰り返しいろんな問題をやってトレーニングをすることで、徐々に慣れていきます。
2. 点と点が線でつながる
民法の学習というのは、知識を、点と点をどんどん線でつなげていくイメージが大切なんです。例えば、今出てきた弁済とか、過失という意味を単体で覚えてもそれだけでは、問題が解けないんです。
それが民放なんです。たとえば法令制限であれば、容積率とか、建ぺい率の単語の意味を覚えればある程度問題に対応して行けるんですけども、民法や権利関係は、単語の意味だけ覚えても、それで問題がすぐ解けるというわけじゃないんです。
これらの単語っていうのは、民法のほかの分野でも頻繁に出てくる単語なので、次の分野にどんどん進んでいくと、「なるほど、そういうことだったのかこの意味は」っていう風に、腑に落ちる部分っていうのが徐々に出てくるようになりますこれが点と点が線でつながるという状態なんです。
はじめての民法攻略法
例えば、今出てきた弁済とか、過失という意味を単体で覚えてもそれだけでは、問題が解けないんです。それが民法なんです。たとえば法令制限であれば、容積率とか、建ぺい率の単語の意味を覚えればある程度問題に対応して行けるんですけども、民法や権利関係は、単語の意味だけ覚えても、それで問題がすぐ解けるというわけじゃないんです。
これらの単語っていうのは、民法のほかの分野でも頻繁に出てくる単語なので、次の分野にどんどん進んでいくと、「なるほど、そういうことだったのかこの意味は」っていう風に、腑に落ちる部分っていうのが徐々に出てくるようになります。これが点と点が線でつながるという状態なんです。これは、仕事教えてそんなことないですか。入ったばっかの会社で「何やってかよくわかんない」じゃないですか。
でも、続けてやってたことで。「こういう事に反映されるんだ」って分かったりするじゃないですか。それと一緒なんです。民法も、けっこうそれと似ております。点と点が線でつながると言う状態です。知識と知識が結びついて、理解につながるという瞬間でございます。この状態になるには、ある程度学習を根気よく進めていくって言う必要があるんです。
途中でやめちゃだめなんですよ。初心者によくありがちなのが、この点と点の点だけを見て、理解しようと時間をかけてしまう人がすごく多いんです。この点だけを見て、一生懸命見て覚えようとするんです。点だけ覚えても問題は解けないんです。もちろん点を理解するっていうことは、とっても大切なんですけども、民法で得点をして行くためには、この点と点同士を線で結びつけていくんです。
星座のように。これは、感覚を覚えることがとっても大切なんです。これは、民法の学習を進めていけば、「ああ、このことか」っていう風にわかる瞬間が多々出てくるようになります。ですから、民法、権利関係については、焦らずに根気よく、そして追い詰めずにある程度開き直って学習をしていくことがとっても大切です。
最初のうちは、チンプンカンプンだったとしても、焦らないということがとても大切です。ちやんと意味分かっいて進める方はそれでいいですよ。ただ、私みたいに、法律など学校で学んだ事ないって方も、宅建受ける方がたくさんいるんです。それで合格するっていう方、沢山いるんですね。絶対に諦めて欲しくないんです。諦める必要ないんです。合格できます。
毎年、民法の壁にぶつかって、出願時点を辞退する人が続出するので、非常にもったいないんです。ここまでで宅建業法と法令制限は、ある程度勉強してきているのに、民放で挫折してやめちゃう人がいるんですよ。ここは、絶対に退却しちゃあ、だめです。わからないのはみんな同じです。
私もそうでしたですから。今は、わからない部分があっても、とりあえず大量記憶法で管理しながら徐々に進めていってください。「あれは、こういうことだったんだ」っていう風に思ところがたくさん出てきます。これは、私が試験勉強している最中もそう思いましたし、今、実務で仕事をしていても、そういう部分がでてきます。
この条文が、こういう時に使う条文だったんだとか。ですね。そういうふうにですね。どんどん線がつながっていくんですよ。点と点を線でつなげることができればできるほど理解が深くなっていくんです。これを味わうと、非常に気持ちが良いです。
(令和01年問07)勉強方法
Aを売主、Bを買主として甲建物の売買契約が締結された場合におけるBのAに対する代金債務(以下「本件代金債務」という。)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1.Bが、本件代金債務につき受領権限のないCに対して弁済した場合、Cに受領権限がないことを知らないことにつきBに過失があれば、Cが受領した代金をAに引き渡したとしても、Bの弁済は有効にならない
買主Bは、売主に対する代金債務を負っています。つまり、物を買ったらお金を払わなければならないと思ってください。債権というのは、請求できる権利のことです。請求される方を債務者、請求する方を債権者と言います。この場合、債務者であるBは、債権者であるAに対して弁済するのが普通です。
当たり前です。例えば、Bさんが不動産大学Aからマグカップを買つた場合、Bは、不動産大学Aにお金を払わなければなりません。ところがBさんは、どうしたのかと言うと、不動産大学Aではなく、Cにお金を払っちゃったんです。「どういう事」ってなりますよね。
「何でCにお金を払うの」て、なりますよね。これが、民法を難しくする原因なんです。どうしても選択肢でこうやって、文章で書いていくと「はあ?」という状況がよくあるんです。たとえば、CがAの関係者だと言って近づいてきて、そのままCに支払った場合なんかですねですが、実際Cは無関係なんです。受領権限がなかったんです。これですね。
突然Cが現れ、みなさんがBだったらどうしますか。これ、普通だったらAに電話して確認しますよね。「今、Cってやつがお金取りに来ているけど払っていいか」と、確認しますよね。ところが、Bは電話一本書けないまま支払っちゃってるんですよね。
つまり、過失があるということなんです。過失とは、ちょっと調べればわかること。これが過失です。このような場合、Bに落ち度がありますから原則として無効なんですよ。弁済は無効です。ただ、問題はこれで終わりではないんです。
このあとCはなぜか、Bから受領した代金をちゃんとAに引き渡しているんです。意味わかんないですよね。Aにちゃんとお金を引き渡したんです。でも、状態いたしましては結果オーライですよね。ちゃんとお金がAに届いたんですから、問題なさそうに見えるじゃないですか。
選択肢では「Aの弁済は、有効にならない」と言っておりますが、これ有効にしない理由ありますか?。有効にならないんであれば、どうなっちゃうかと言うとBは、さらにAにマグカップの代金を払わなければいけない。という結論になります。
これおかしいですね。Aは2倍も儲かっちゃっている。実際問題、極めて理不尽です。そこで、民法では、受領権者以外の者に対する弁済について、債権者がこれによって利益を受けた限度において効力を認めています。
要するに、債権者の手に渡ったお金の限度におい弁済した事にしょうと言うことになっています。ですから、Bの弁済は、Aが利益を受けた限度において有効です。だから、答えは×です。
こんな感じですね。難しい言い回しは結構出てくるんですけども、だんだん慣れてきますので、今は焦らずに徐々に慣れていくことを意識しましょう。