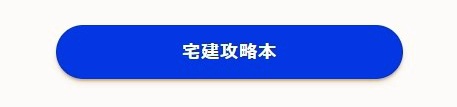宅建過去問の正しい使い方とは
【神回】宅建不合格者の共通点、それは過去問の使い方を間違えていることに原因あり!一発合格するなら絶対知っておくべき、過去問の正しい活用術を初心者向けに徹底解説。
過去問題はテキストとしての重要な役割
宅建過去問題を支えるための情報を宅建のテキストで吸収していく。 これが宅建テキストの役割です。
中心は宅建過去問です。
(例)「未成年者が利息受領すること」これは、親の同意がいるかいらないか。といった問題があったとします。利息については、親の同意なしで受領することができます。これがいわゆる過去問題に乗っていて、問と解説だったとします。これを読んだときに、なるほど未成年者というのは、利息を受領するときに親の同意、親権者の同意はいらない。法定代理人の同意もいらないということになります。
じゃあ、未成年者というのは「何だ」ということになります。もしわからなかった場合に、そういった言葉をテキストで調べるわけです。そうすると未成年者は、18歳未満の人を未成年者と言います。なるほど、そういうことなのかということがわかります。じゃあ、「同意を得なきゃならないものはあるのか」ということになります。
逆に「同意を得なくてもできるものがあるのか?」こういったものをテキストで見ると周辺に書いてあります。こういったものを一緒に調べてしまうわけです。そうすると、利息は受領できる。でも元本を受領する場合は、同意が必要になってきます。そういったこがテキストの周辺に書いてあります。
そうすると、「あーなるほど」ということで、これも一緒に覚えられるわけです。つまり、ひとつの過去問から周辺の事実を覚えていくと、こういったことができるわけです。これを、テキストを使ってやっていくわけです。確かに重要なポイントは過去問題です。
これを単純に覚えようと思ってもなかなか覚えられないんですね。いわゆる、いろんな付加情報をつけて覚えていく。そうすると、逆に覚えやすくなるわけですね。この一つを覚えるために、周辺を一緒に覚えることで記憶しやすくなるということです。 こういったことを、過去問を使いながらやっていくわけです。
いろいろな問題をやっていくと重なることがあります。これが復讐している部分ですね。すると同じような問いを問われた時に、パッとテキストを見て復習できるわけですね。
こういった使い方をするわけです。あくまでも宅建独学の中心は過去問題です。宅建の過去問題で分からない言葉、条文全体、こういったものをきっちり宅建テキストを使って勉強していくことです。
過去問題の選び方
宅建の過去問題は、宅建独学勉強のメイン教材になります。 選択には一番神経を使うところです。 一番大切なのは宅建の過去問題の解説がどうなっているかです。 判断する方法は、問題の解説が単純に説明してあるものは避けることです。
過去問の間違った使い方
- 宅建独学では、一度目を通した.宅建過去問題で再度、模擬試験を行っても意味がない。
- 宅建独学は、過去問題の解答が頭に入っているから高得点がとれて当たり前。
- 宅建独学では、過去問題の解答の出し方ばかり覚えていて、まったく応用が利かない。
- 宅建独学では、過去問で40点とれたなどと喜んで方向性を誤る。
- 宅建独学で、宅建過去問題を使って模擬試験をする場合、1~2か月で始めるのは、遅すぎます決して間違った使い方はしないようにしましょう。
過去問題の正しい使い方
- 最初から宅建問題の解答を出すことは避けましょう。
- 宅建問題の1肢を読む
- 宅建過去問の解説を読む・・なぜこうなるのかわからない・・
- 宅建のテキストで確認する・・マカーでチエックする。
- 「じやあこうなるとどうなる」など、疑問点がある・・
- 宅建のテキストで確認・ネツトで質問してみる・・理解する
まとめ
宅建の過去問題は間違った使い方をしないようにしましょう。何回も、何回も単純に解いても時間のムダ、ムダ、ムダです。 宅建試験の勉強をするに当たり誰もが、みんな同じように 必ずや宅建過去問題集を手にしているかと思います。
過去問集とは、実際の過去の宅建試験を集めた学習教材となるため、本試験に合格するために必要な教材といえます。 宅建の勉強は過去問題で勉強する。 いやいや、テキストではないですか?
と質問される方がいますが、これ間違っています。 宅建テキストで勉強している限り。はっきり言って「合格できません」 宅建試験に合格するには、過去問をいかに理解して応用できるかが必須不可欠といえるでしょう。