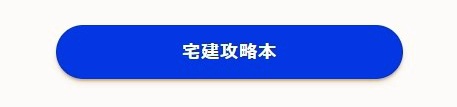初めての宅建勉強 方法でお悩みの方へ
初めて宅建を学ばれる方! 勉強方法は慎重に選択しましょう。
はじめて宅建試験に臨まれる方で、法律をまったく学んだことのない方。
独学はお勧めできません。
宅建勉強では、民法が大きな壁になります。
自己流で学ぶと、法律が正しく理解できません。
法律を誤った内容で覚えてしまうと、修正にムダな時間がかかり、本試験に間に合わなくなります。
「もう一年やり直し」という最悪の結果になるかもしれません。
宅建独学のデメリット
独学のデメリット
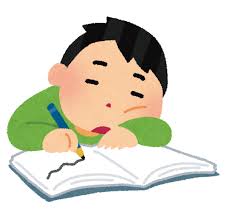
ハードルが高いなあ!!
- 自分でスケジュール管理をしないといけない 。
- どの教材を選べばいいかわからない。
- テキストを自分で読み進めないといけない。
- 教材の使い方がわからない。
- わからなくても質問できない。
- 自分の今の勉強方法で合っているのか不安。
- モチベーションを維持するのが大変。
- などなど、独学のメリットに比べ、挙げればキリがないほど数多くのデメリットが存在しています。
独学のメリット
- コストが安い!
- 誰でもいつでも手軽に始められる!
宅建独学に向いていない人・向いている人
独学に向いていない人
・法律を学んだことがない。
・年間スケジュールが立てられない。
・勉強の要領がつかめない。
独学に向いている人
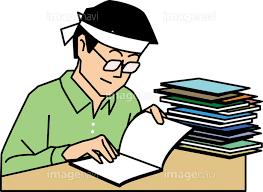
まかせろ!!
・法律を学んだことがある。
・テキストだけで理解できる 。
・テスト慣れをしている。
独学に向いてない方、通信講座を選択する道もあります。
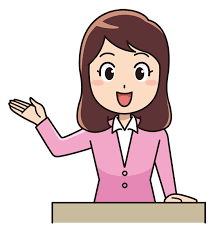
スケジュール設定。疑問点の解決OK
「法律を一度も学んだことがない」こんな方は、通信講座をお勧めします。初めて宅建勉強を始めるには、宅建の勉強方法で、「良いとこ取り」をしたものが、「通信講座」です。 今では、スカイプで講師に質問できるところもあります。
どの勉強方法が宅建試験の合格への近道なのかは検討して選択しましょう。
どの勉強法でも「自分に合った勉強法」かどうか、というのがポイントになります
私が宅建独学を選んだ理由

資格を取ることに決めました。
初めての人事異動で、本店に異動することになりました。 そこはFP一級の人や司法書士など恐ろしいくらい高資格のひとばかり職場でした。あちこちの支店へ指導にいく教員の集団みたいなところです。
電話で応対するのは、支店からの法律相談を受け付ける専門家の方ばかりで、とにかく自分の基礎知識がなさ過ぎて、いくら先輩職員に聞きながら対応しても限界があると感じました。 そこで、思い切って「宅建」の資格をとろうと勉強を始めることにしました。

すごい資格をもってるな!!
私が独学を選んだ理由は、通学講座に通うというのは、はじめから論外でした。過去に、教材がどんどん送られてきて、テスト問題を月に1度提出するのですが、問題を解くための勉強となりなにも身につかなかったという苦い経験からです。
又、通信の費用も馬鹿にできない高額でした。今回の宅建にしても3万~5万円かかりそうでとてもわたしの小遣いから捻出することはできません。
ということで、費用と時間の兼ね合いから「独学」で宅建試験に挑戦することになったというのが理由です。 全くの初心者でも独学で宅建に合格できる!と先輩から聞きました。 ちなみに私は、高卒でしたし、法律の勉強など一度もしたことのない、まったくの初心者でした。

独学で合格!!
法律の予備知識がない、こんな私でも、独学で宅建試験に合格することができたわけですから、皆さんもきっと独学で合格できるはずです!
宅建試験に挑戦するための勉強法としては、コストが最も高くつく、通信講座やスクール講座もありますが、コストが最も安くつき、なおかつ手軽にできるのは、やはり「独学」です。