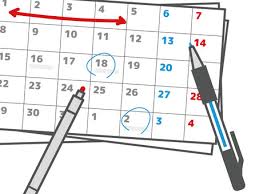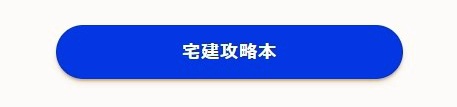宅建試験勉強は3月からのスケジュールが大切です

どうしても合格したい・・どうすれば・・
宅建試験に間に合う3月からのスケジュール
たとえば、3月4月5月6月7月で10月の中旬で宅建試験、という流れになるとします。一般的な宅建通信講座などは、標準の学習期間を6ヶ月と設定している場合が多いです。6か月ですと、だいたい「4月の中旬の辺から合格できる」ということを言っています。
これも条件次第ということになります。今までの知識なしで、法律の勉強もしたことが無い方が勉強始めて最短4ヶ月で合格しています。最短で4ヶ月ということは、6月の中旬から始めても間に合うということですが、これでは厳しい条件がつけられます。
その条件は、ちゃんと効率的に勉強を開始した時から理解できていないとなかなか難しいね。それは、高速でどんどんどんどん理解学を進めていくということです。調べる時間は、ほぼないと考えてください。
もちろん少し調べる程度のことはありますが、一問当たり20分程度使っていたら、物理的にも難しくなってきます。
どんどん理解をしていかないと、いけないって言うことになります。それがちゃんとできれば、「4か月でも合格できます」ということです。それには、「ちゃんとした教材と個別指導をしてもらう」そうじゃないとなかなか難しいわけです。
ただ、独学であったとしても、ここまでの期間の間で高速で理解する学習の仕方を習得していれば大丈夫です。それができていなかったら、なかなか難しいことになります。もう、来年目指しましょうということになります。
自己管理、勉強の仕方を間違えると間に合わない
習慣を変えるためには、自己管理が必要ですね。モチベーション管理とか、精神的なものだとか、自分でコントロールできていかないとなかなか難しくなります。
やる気がない時であったとしても、ちゃんと勉強する。時間を作れるようにコントロールしていく。自己管理して、これまでできていないのであれば、おそらくこれからなかなか難しいです。相当、気持ちを切り替えていかないとなかなか難しくなります。
習慣を変えるというのは、それぐらい難しいことです。私も、勉強は早い段階で始めましたが、勉強の仕方についてはなかなかうまく行きませんでした。私は、勉強を始めたのは、12月の終り頃からはじめました。それから7月ぐらいまでずっと、過去問丸暗記、テキスト丸暗記でした。
もちろん、過去問の解説読んで分からないところは、丸暗記しているので、その問題は解けるわけですよね。しかし、実際見たことない問題は全く解けなくて、過去問でも解いたことのないのは18点くらいでした。この勉強の仕方をやっていたら、点数は上がるのかと考えました。
しかし、「伸びないな」と、私は感じました。なんと言っても理解してないから。普通に考えたとしても無理です。相当、角度を変えてきたり、引っ掛けたりしてくるので、「無理だ」ということでけじめをつけてしまいました。
丸暗記から理解学習へ変えてみる。
7月からは、高速理解とは行きませんが、理解学習をずっとやり続けました。一日で勉強ができても、2問とか3問とかそんなレベルでノロノロとやりました。
それが良かったです。そこで、ちゃんと理解学習をしていた結果、それにどんどん慣れてきて調べ方も身についてきて、そこからどんどん早くなってきました。やっと8月くらいから実力が上がりだして合格しました。感想としまして、ちゃんと理解学習というものができてこないと合格はなかなか欲しいと思いました。
落ちている方のほとんどは、勉強はしているけども理解していないんですよ。それは、勉強していないということです。衛生管理者などの資格試験があるんですけども、1か月くらいの丸暗記で合格してしまうものもあります。
宅建はとそうじゃないので、丸暗記したところであまり勉強にはならないですね。
それで、本当に何回も、何回も落ちる方がいるんですよね。話では10回落ちている方の話も聞きました。10何回も落ちても受験するって、凄いなぁって思ったんですけどね。結局は、理解していないゆえに実力が上がらないんですよね。
私が知っている限りでは、7回8回が最長だったんですが、ちゃんと理解さえすれば一回でサラッと合格します。本当にやった勉強時間って言っても、そんなに差がつかないんですが、1日に2時間やっていても勉強の質というもので大きく変わってくるんですよ。
まとめ
丸暗記学習から、質の高い理解学習に切り替える。そして、自己管理とスケジュール管理をしていくことです。自分の時間管理はそのひとによって違います。
今の試験は、丸暗記では対応できません。特に個別問題などは、全問正解しないと解答が出ません。
基本問題でも、奥が深くなっていてあやふやな記憶では正解しません。なぜこうなるのか、理論づけて勉強しましょう。
やる気なくなったと時は、「勉強できるようにするためには、どんな気持ちにならなきゃいけない
か」 「自分は合格したい」それをモチベーションにして、やる気がなくなっても、「勉強やらなかったら合格しないよ」自分に活を入れて頑張ることです。
スケジュールが遅れている場合は、「日曜日にやる」など対応策を考えて実践していく。「宅建業法が終ったら、次は、民法を学習していく」というようにサイクルをうまく回していく。丸暗記学習に傾いたら、すぐに、質の高い理解学習に変換し軌道修正する。
このようにして、スケジュール管理と、モチベーション管理をしていきます。
4月あたりから理解学習ができてこないと難しくなってきますから、早めに理解学習の習得をしてください。より早い段階から理解学習した人の方がどう見ても合格率がいいですね。
今年こそは頑張って、宅建に合格しましょう。